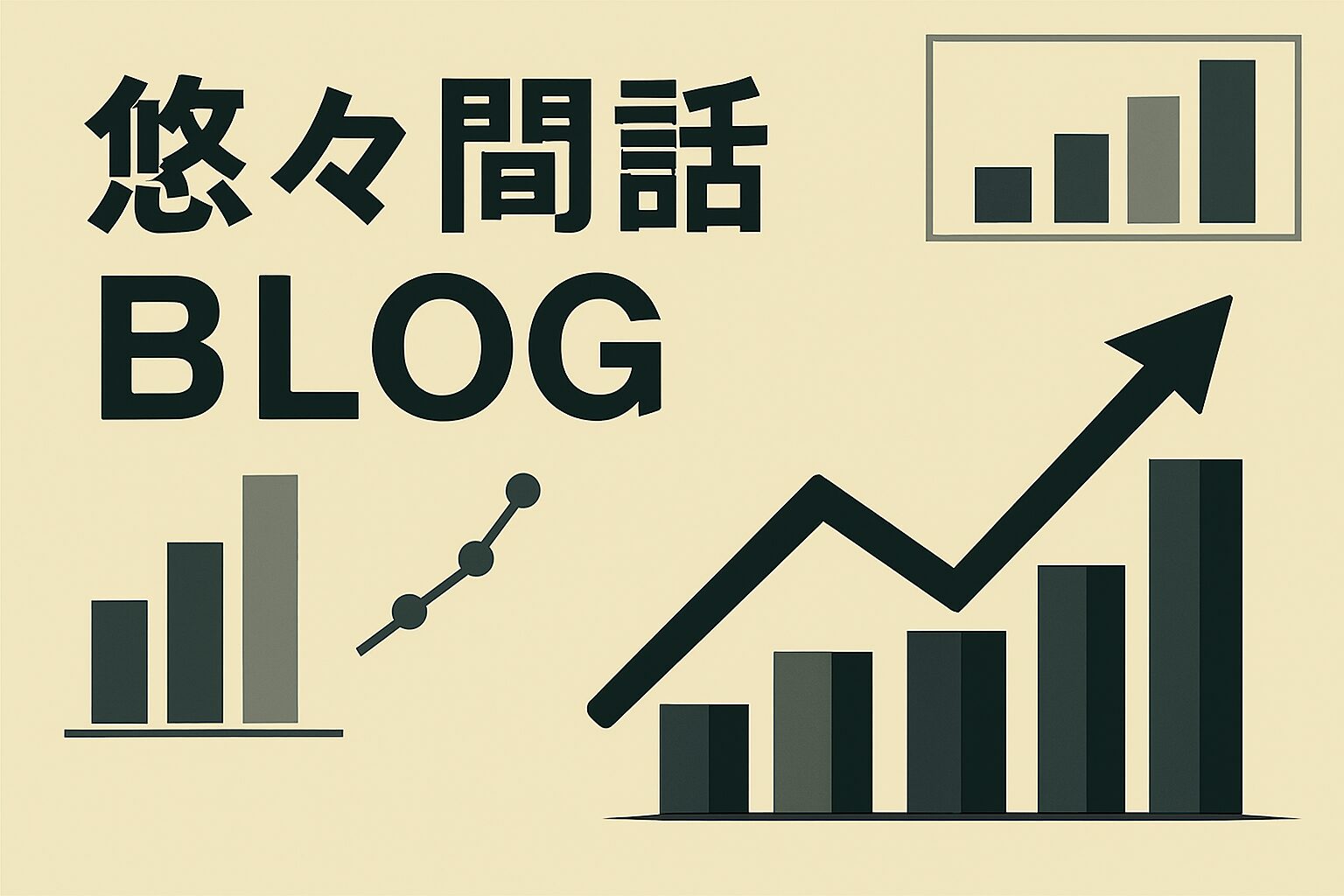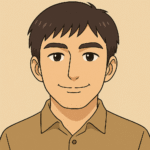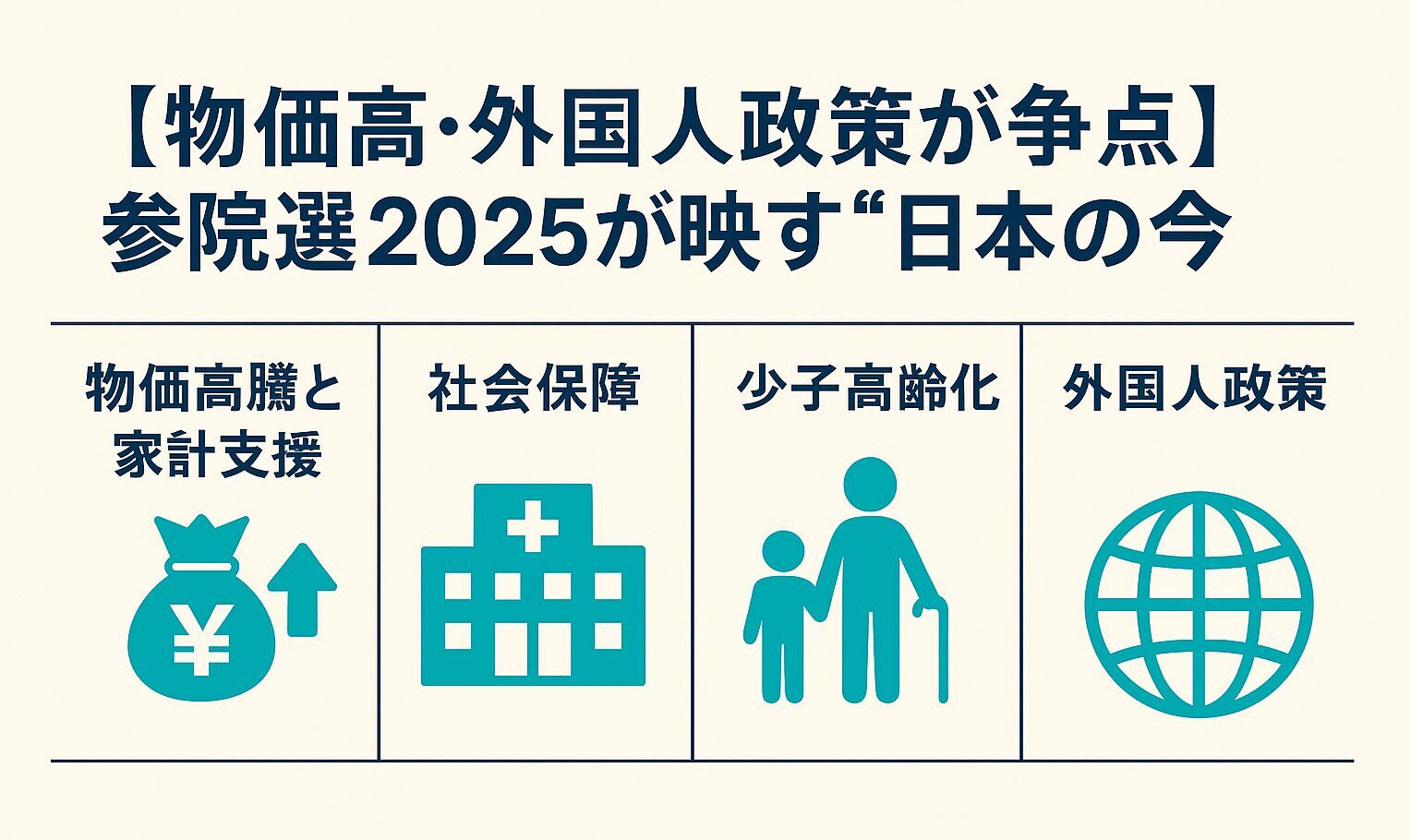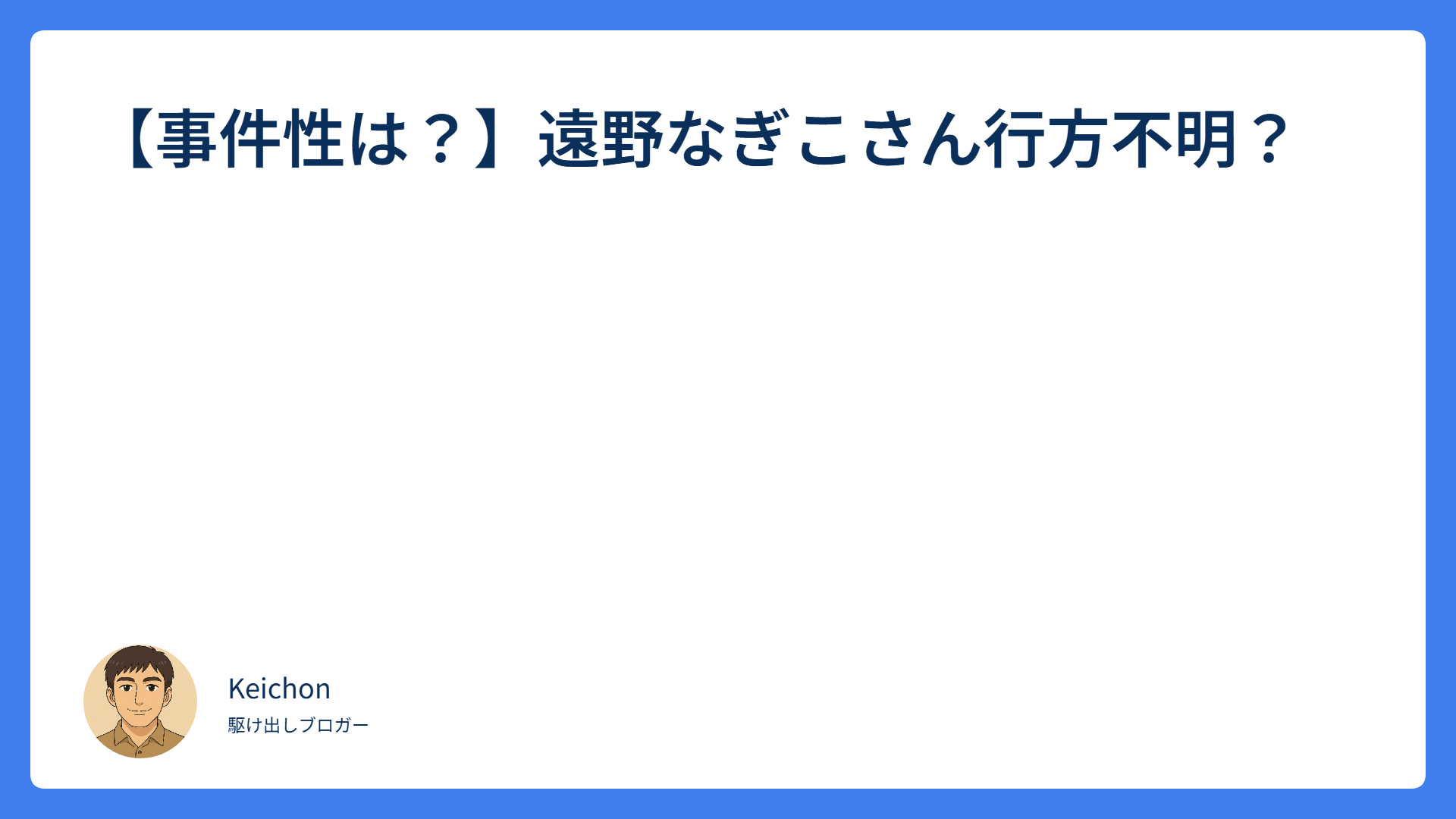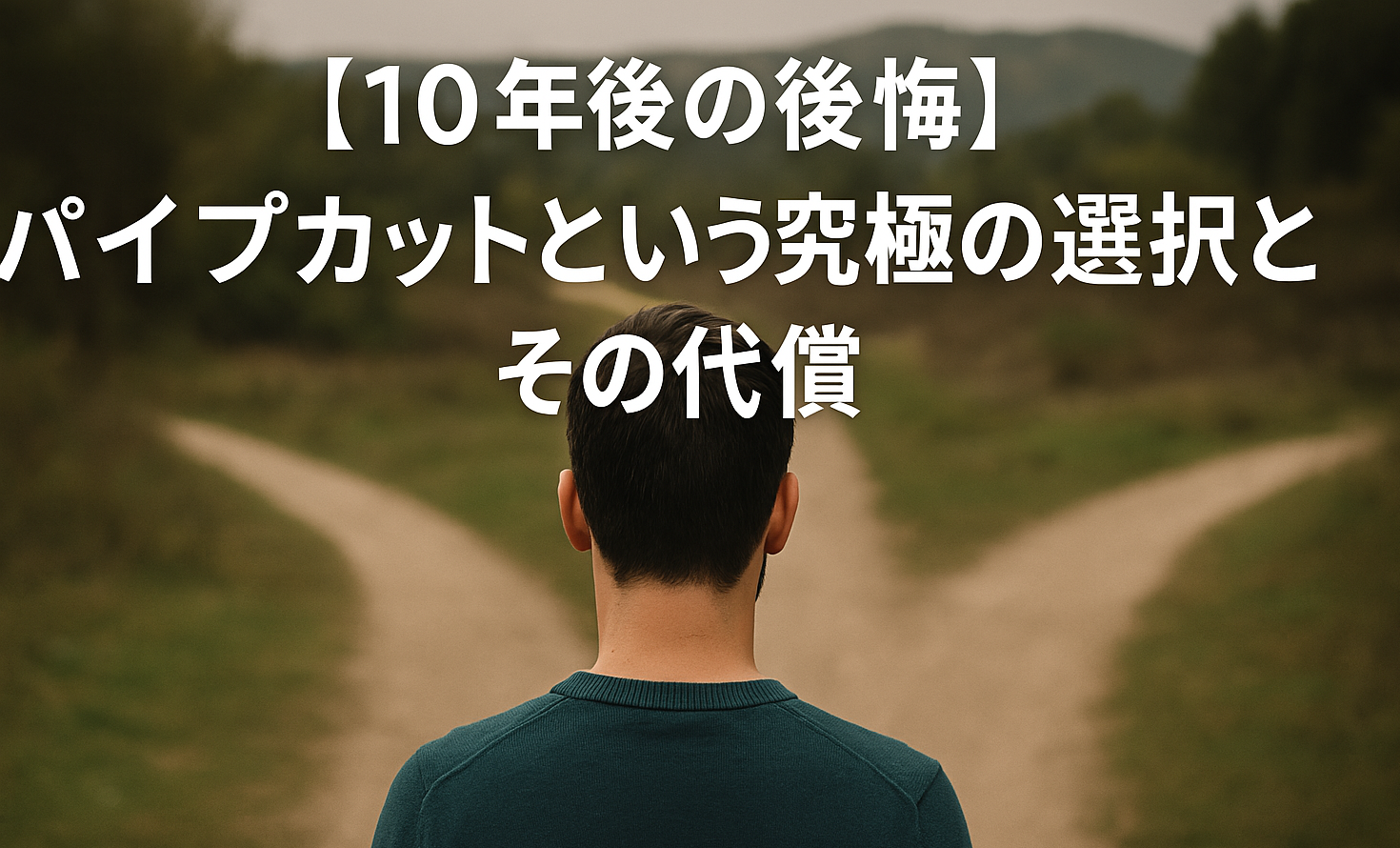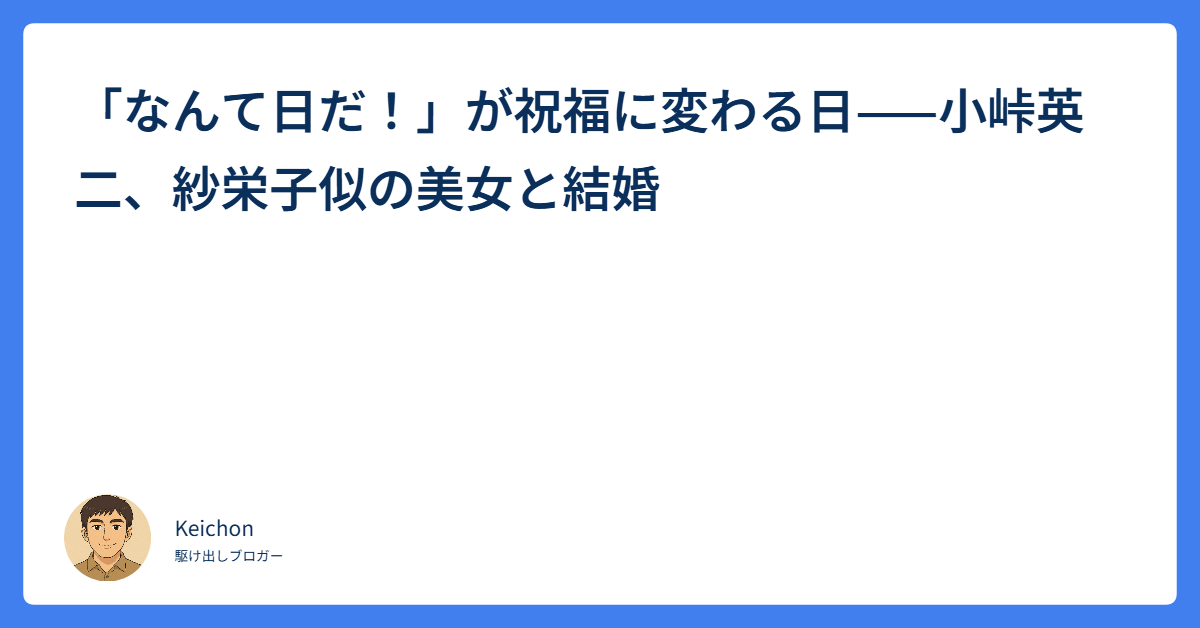【女子寮に彼?】 トランス女性受け入れ論争のリアル
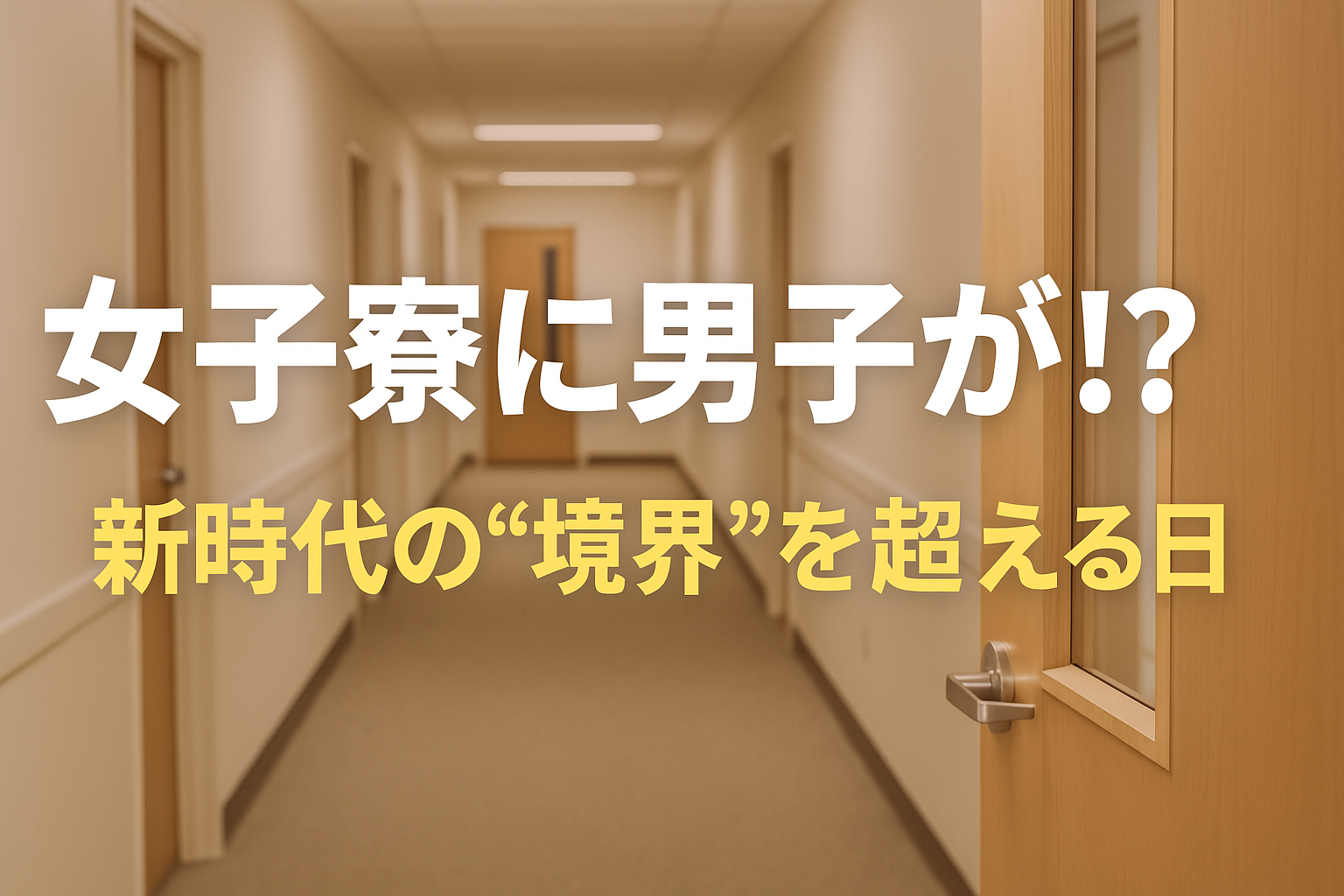
🌸多様性の扉を開くとき──トランスジェンダー女性と女子寮の現在地
2025年7月、福岡女子大学が生まれたときの性別は男性だが性自認が女性である学生(いわゆるトランスジェンダー女性)を2029年度入学分から受け入れる方針を発表しました。
SNSやニュースでは「多様性の尊重」と「女子寮での安全性確保」が対立するかのような議論が噴出しています。
全寮制という制度の特性が改めてクローズアップされている状況です。
女子大の伝統的な“女性だけの空間”が、いま大きな転換期を迎えつつあるのです。
🏫女子大という空間の意味
女子大学は長らく「女性が安心して学び、生活できる場」として機能してきました。
講義やゼミだけでなく、寮生活は私室やトイレ、浴室を他者と24時間共有する特別な環境です。
そこでは「性別による偏見や視線」を気にせず、友人と本音で語り合うことができる安心感が重視されます。
一方で、その安心感がトランスジェンダーの受け入れとどう両立できるかが最大の焦点となっています。
💬当事者の声──「24時間おびえて暮らす可能性」
トランスジェンダー女性のかえでさん(仮名)は、共学大学の女子寮での経験から次のように語ります。
「スッピンだと男性に見られることがあって、鏡の前でため息をつく毎日です」
「浴室や更衣室で“バレるかもしれない”という緊張が24時間続くのは、本当にしんどい」
彼女にとって女子寮は居心地の良いはずの場所でありながら、自分自身が“秘密”を抱えたまま共同生活を送る苦しさと隣り合わせなのです。
👭寮生活をともにする女性たちの声
初めての寮生活なのでプライバシーは大事です。身体的性別に基づく安心感も理解してほしい。
海外ではジェンダー多様性とシェアスペースに関するルールが整備されていて、日本も前向きに議論できると期待しています。
多様性を尊重したいけれど、不安や違和感を抱える人がいない設計が必要です。きちんとしたガイドラインと配慮があれば安心できます。
と意見を寄せています。
⚖️多様性と安心のバランス
SNS上には「性自認を尊重すべき」「身体的性別で安心感を担保すべき」と両極端な声が飛び交っています。
しかし、どちらか一方を優先するだけでは解決しません。
むしろ重要なのは「誰もが安心して生活できる具体的措置」を大学が提示し、寮生同士で信頼関係を築くことです。
そのためには、プライバシー保護や個室の増設、専用浴室の導入といったハード面の整備と、相互理解を深めるソフト面のケアを両立させる必要があります。
🌍海外の事例と日本の課題
米国の大学では、ホルモン治療や戸籍変更の有無を基準に個室やユニバーサルルームを割り当てるケースが増えています。
しかし日本では戸籍変更のハードルが依然高く、多くが自己申告での対応を迫られる状況です。
これからは、海外のガイドラインを参考にしつつ、文化的背景を踏まえた日本独自のルールや支援体制を構築することが今後の大きな課題と言えるでしょう。